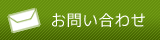PCBは、絶縁性、不燃性などの特性により、トランス(変圧器)、コンデンサ(蓄電器)といった電気機器をはじめ幅広い用途に 使用されていましたが、昭和43年にカネミ油症事件が発生するなどその毒性が社会問題化し、我が国では昭和47年以降その 製造が行われていません。
一方、すでに製造されたPCBを処分するため、民間主導によるPCB処理施設設置の動きが幾度かありましたが、施設の設置に関し 住民の理解が得られなかったことなどからほぼ30年にわたりほとんど処理が行われておらず、結果として保管が続いている状況 にあります。しかしながら、保管が長期にわたっているため、紛失したり、行方不明になったトランスなどもあることが判明し、 PCBによる環境汚染が懸念されています。
世界的にも、一部のPCB使用地域から、全く使用されていない(北極圏など)への汚染拡大が報告されたことなどを背景として、 国際的な取り組みが始まっており、欧米諸国ではすでにPCB廃棄物の処理体制は相当進んでいます。そのため、我が国においても PCB廃棄物を処理するための体制を速やかに整備し、確実かつ適正な処理を推進することが急務となってきました。このような状況 から、平成13年6月22日に 「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」(以下、「PCB特措法」と いいます。)が公布され、同年7月15日から施行されました。(上記リンクは環境省PCBページ)
PCBとは Poly Chlorinated Biphenyl(ポリ塩化ビフェニル)の略称で、ポリ塩化ビフェニル化合物の総称であり、 その分子は保有する塩素の数やその位置の違いにより離婁的に209種類の異性体が存在します。中でもコプラナーPCB と呼ばれるものは毒性が極めて強く、ダイオキシン類として総称されるものの一つとされています。
性質として、溶けにくい、沸点が高い、熱で分解しにくい、不燃性、電気絶縁性が高いなど科学的に安定しているため、 電気機器の絶縁油、熱交換器の熱媒体、ノンカーボン紙など様々な用途で利用されてきました。 現在は輸入・製造共に禁止されています。
脂肪に溶けやすいという性質から、慢性的な摂取により体内に徐々に蓄積し、様々な症状を引き起こすことが報告されています。 PCBが大きくとりあげられる契機となった事件として、カネミ油事件があります。この事件は、米ぬか油(ライスオイル) 中に、脱臭工程の熱媒体として用いられたPCB等が混入したことが原因で、昭和43年10月、西日本を中心に広域にわたって 米ぬか油による食中毒が発生しました。当時の患者数は約1万3千名に上ったと言われています。
一般にPCBによる中毒症状として、目やに、爪や口腔粘膜の色素沈着などから始まり、ついで座瘡様皮疹(塩素ニキビ)、 爪の変形、まぶたや関節のはれなどが報告されています。
PCBは、その特性から自然環境下で分解せず流出した場合、私たちの生活環境に著しく悪影響を与えるため、PCB廃棄物は廃棄物処理法 の特別管理産業廃棄物保管基準に従い、保管することが義務付けられています。使用中のPCB内封電気機器については、電気事業法、 電気設備に関する技術基準及び電気関係報告規則が適用されています。
上記のいずれの場合も、保管及び使用の届出が義務付けられています。
|